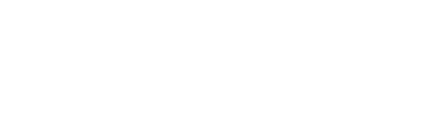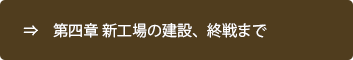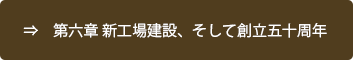秋山錠剤物語第五章 戦後の再出発
第五章 戦後の再出発STORY
目黒・東町時代
戦後、「秋山」は、工場をなくし、市郎は右足負傷という困難の中から再出発しなければならなかった。その再スタートを支えたのは、当時まだ、学校を出たばかりの若い秋山義郎二代目社長であった。
「終戦直後の1年というものは、本当にやみくもに生きた1年でした。父は寝たきり、家族は福島のいわきの方に疎開。動けるのは私ひとりでした。まだ社会のことなど何も知らない私でしたが会社再建のためにはぜいたくなことはいっていられなかった」(義郎・談)
義郎は、戦争末期、明治薬専を卒業すると江東製薬に就職、世田谷にある研究所に勤務していたが、昭和20年の11月には、江東製薬を退社、父・市郎を助け、「秋山」再建に乗り出すことになった。
5月の大空襲で全焼した工場を再建することは当時まず不可能だった。ただ、機械は焼けたといっても駆対は残っていたので、修理すれば使用可能であった。そこで、義郎は、まず手狭な場所でもいいから、建物のある工場を探した。20年も末になると、どうにか敗戦ショックから立ち直った産業界は再建の手探りを始め、製薬業界でも、三宝製薬、太陽製薬が復活の兆しを見せ、それに伴って「秋山」の錠剤技術が求められたのである。
工場はなかなか手頃なものが見つからなかったが、21年になって、目黒区東町に、プレス工場だったものが売りに出されているのを見つけ、義郎はそれを、当時の金、七万円で買い求めた。現在の武蔵小山付近である。
「資金を集めるのが大変な仕事だった。機械をいくつか売っておカネを作りましたがそれだけでは足りず、戦争前のお得意様にお願いして借りました。それでも私はまだ20代の若者。足もとを見られ、ずい分と損な買物だったようです。」(義郎・談)
秋山錠剤株式会社と改名
新工場は28坪。狭く、プレス工場を改良した工場だから不備な所が多かったが、ぜいたくはいっていられなかった。昭和21年の8月の暑い盛りに、「秋山」は再出発した。戦後の「秋山」のスタートである。
再開にあたって、新たに組織を株式会社にし、名称も「秋山錠剤株式会社」とした。社長は、秋山市郎。そして、専務には秋山義郎が就任した。当時、市郎はまだ足の負傷がよくならず療養生活を送らねばならなかったので、実務は、若い義郎が担当することになった。
工場は、戦前の最盛期に比べれば粗末なものだった。打錠機の台数は、7~8台に減ってしまったし、乾燥機は再び電熱乾燥。出来あがった製品の配達は、再び自転車とリヤカー。
従業員の数も、7~8人。中には、巣鴨プリズンに収容されていた「戦犯」もいた。
「当時、巣鴨では、戦犯と言っても、昼間は民間の会社に働きに行って、夜になるとまた巣鴨に戻るという人達がいたのです。とてもまじめな人達でしたし、知人の紹介もあったので仕事を手伝ってもらいました。戦後の混乱の時代ですから、今から見れば不思議なことがいろいろあったのですね」(義郎・談)
戦後の「秋山」の再開第一号製品は、太陽製薬の「ビタレイ」だった。戦前の「秋山」の主力製品である。三宝製薬の「ジアトミン」も手がけた。だが、昭和21年といえば、まだ、食糧難、ハラペコ時代である。薬が売れる時代ではなかった。
それでも、二代目の義郎は、戦前の「秋山」とは違ったものを出そうと努力した。そのあらわれが「広告宣伝」である。
「『秋山』の場合、一般消費者よりも製薬会社が“お客様"でしたから、目黒に移ってしばらくしてから業界新聞に広告を出すことを考えた。
『秋山錠剤が復興しました!』はじめての広告はそんなコピーでした。私が自分で広告も作った。なにしろ、まず、戦前の取引先に、『秋山がまた仕事を再開した』と知らせることが先決でしたから、そんな広告になりました」(義郎・談)
広告の効果はあった。戦争の前の取引先も序々に、復興しつつあり、再び「秋山」に仕事を出してくれるようになった。
再び、戸越に移る
目黒・東町の戦後工場は、フル活動していたが、義郎としては、やはり以前、工場があった戸越の方に戻るのが願いだった。土地も広いし、やはり「秋山錠剤」発祥の地である。それに、当時、戸越は、星製薬あとに進駐軍がいて、そのために電力事情が良く、停電などめったにないという、有利な点もあった。そこで、義郎は、父の市郎の同意を得て再び、戸越に戻る決心を固めた。
目黒の工場を機械込みで約20万円で売却し、それを元手に、戦前、工場があった同じ場所に、同じ広さの平屋の工場を建てた。以前は、土地は借地だったが、この時に、土地も買入れた。当時は、まだ、セメントやガラスといった建築資材が手に入りにくい時代だったが、義郎は、何度も厚生省に足を運び、配給物資を得て、ようやく工場を完成させた。
昭和23年のことである。あたりにはまだ焼け跡が残っていた。
この頃、市郎は、ようやく足の負傷もよくなり、再び第一線に復帰した。市郎が経営の現場に戻るようになってからは義郎は、技術の改良に力を入れた。当時、打錠機は7~8台に数が減っていたので、量産化を図るために、改良せざるを得なかったのである。
昭和23年から24年にかけては、まだまだ、薬の売れる時代ではなかった。ましてや消化剤や、健康食品が売れるほど余裕のある時代ではなかった。薬よりも食糧の時代である。当時「秋山」が扱っていたのは太陽製薬の「ビタレイ」、江東製薬のサルファ剤「チアゾール錠」、鳥居製薬のサルファ剤「ダイアジン錠」などであった。
工場全焼
昭和23年はまだ薬の売れる時代ではなかった。そのため「秋山」では、錠剤技術を生かして、医薬品以外にも、サッカリンのお菓子、ボタン成型、固形シャンプーなども手がけるようになった。とくにⓎ油脂の固形シャンプーの仕事は多く、一錠5gのものを1日1トンも打錠した。一時は医薬品よりシャンプーのほうが主になったこともあった。
だが、23年の冬になって、この固形シャンプーの原料の油に引火し、工場はあっという間に火に包まれて全焼してしまったのである。「秋山」にとっては二度目の火事である。空襲も含めれば三度目となる。戦後の混乱期のことで火災保険にも入っていなかったので損害は甚大だった。しかし、幸い住居(工場に隣接していた)は焼けなかったし、三田に小さな下請工場を持っていたので、もとの場所に20坪の工場を建て直した。火事になって半年後の昭和24年の6月のことである。打錠機は駆対が焼け残っていたので、改良し、工場も再開させた。
序々に復興
昭和24年は、まだまだ日本の経済は回復せず、全体的に不況だった。工場を再開させたものの、固型シャンプーの仕事もなくなり、しばらく低迷が続いた。
昭和25年に朝鮮戦争が勃発。隣国の悲劇はだが同時に日本経済の戦後復興の引金にもなった。産業界は活況を取戻した。医薬品界も序々に立ち直り、「秋山」の戦前からの発注先もいくつかこの時期に復興、「秋山」も忙しくなった。
このころ、戦争を感じさせるものとして、溶かして麻酔に使う局部麻酔の注射錠剤を作ったりした。仕事がふえてくるに従って、打錠機、乾燥機(ガス式)の数も増やしていった。昭和29年になると砂糖の事情もよくなったので糖衣部門を復活、3台の糖衣機(30インチのパン)を置いた。糖衣機はすぐに6台に増えた。
昭和28年はNHKのテレビ放送が開始され、“家電ブーム"が起こった年。この頃から、日本経済はいわゆる高度成長に入る。昭和30年は“神武景気"、佐久間ダムが完成、そしてソニーのトランジスタラジオが発売された年。そして昭和31年に発表された「経済白書」は“もはや戦後ではない"と宣言した。
医薬品の生産高もこの頃には飛躍的に上昇した。昭和30年には年間生産額895億円、翌31年には一気に1037億円に増え、その後も30年代には毎年、対前年増加率が10%を超える成長を示した。
「秋山」もこの頃には完全に復調していた。トランジスタ・ブームの頃には、日本電気のトランジスタに用いる乾燥剤の仕事なども手がけたが、主力は完全に医薬品になっていた。
高度成長時代
昭和30年代は、世の中が落着きを取戻し医学も“治療から予防医学へ"変わりつつあった。そしてそれに伴い薬も、栄養剤、総合ビタミン剤、ホルモン剤が増えていった。やせる薬などが登場したのもこの頃。まさに戦後は終わったということの一例であろう。
そのころ、義郎は名古屋の陶器貿易商社である、熊谷商店社長熊谷鎮雄の長女、熊谷和枝を嫁に迎えた。昭和29年2月のことである。翌昭和30年には長男、泰伸が誕生し、秋山家も新たな局面を迎えていた。
こうして昭和30年代に入って「秋山錠剤」の基礎は固まっていった。昭和33年には、ミノファーゲン製薬(当時の社長は東京二区選出の衆議院議員・宇都宮徳馬氏)から、「グリチロン錠」の大量の注文があり、それを機に、工場を総二階に増築(約50坪)、包装機を置いて包装工程をも加え、「秋山錠剤」は大きく発展していった。