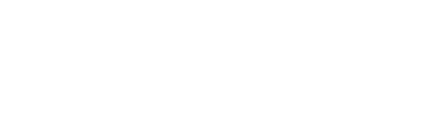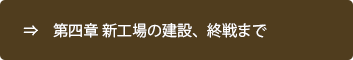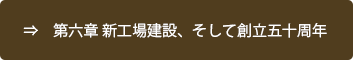秋山錠剤物語第二章 上京、星製薬時代
第二章 上京、星製薬時代STORY
上京を決意

父・義徳は後妻を娶るが27歳の若い継母で秋山家に溶け込めず、秋山家は経済的にも家庭的にも暗い日が続いた。父・義徳の商売は転々と変わった。製氷屋を開き、氷を売ったりもした。市郎は家のために働き続けた。好間炭鉱の測量技師の助手として炭鉱夫と一緒に鉱内に入ることもあった。しかしそうした努力も甲斐なく秋山家の経済状態は好転せず、市郎も20歳を過ぎて自分の将来を真剣に考えるようになっていた。
東京に行こうと決心したのは22歳の時。このままの生活では自分も秋山家もよくはならないと判断した市郎は東京の親類(実母の弟)を頼って上京の決心を固める。東京に行ったら何をするか具体的には考えてはいなかったが、当時習い、覚えていた時計修理の技術を東京で向上させ、行く行くは郷里の平町で時計屋を開こうというばく然とした将来計画をたててはいた。父・義徳も、市郎の東京行きに反対しなかった。
「当時、将来、製薬会社を設立することになるなど夢にも思っていませんでした。私としては、なんでもいいどんな仕事でもいいから没落した秋山家を再興したい、その気持ちでいっぱいでした。東京に行くからには成功するまで決して故郷に帰るまい、と切実に思っていました。」(市郎・談)
こうして市郎は、大正5年10月17日、平町から生まれて初めて汽車に乗って上京したのである。
星製薬に入る
しかし、欧州の戦争が終結に近づくと東京計器では注文も減少し、一時は5百人近くいた信管製造部も市郎を入れてわずか数名に減ってしまった。東京計器では信管のあとに探照灯などを作ったりしていたが、市郎はこのままでは故郷を出て上京した意味がない、なんとかもっとおもしろい仕事はないかと考えていた。ちょうどその頃義理の叔父・志賀富穂(母の妹きみの夫)が、躍進を続けていた星製薬株式会社の工場の包装部長だったので、その紹介で、大崎にあった星製薬の工場に、一職工として就職することになった。
大正6年、市郎が24歳の時である。市郎とクスリとのはじめての出会いであり、この就職が今日の「秋山錠剤」を作ったともいえる。星製薬は、星一が明治37年に設立した製薬会社で、当時、斬新な、アメリカ式の経営で話題を集めていた。星一も、福島県の出身。秋山市郎の大先輩であり、親類でもある。(市郎の母・ヒサの弟・久介の後妻になったのが、星一の妹・あきである)星一は、明治のはじめ、単身でアメリカに渡り、12年間にわたる苦学生活を体験。帰国して、明治37年に「イヒチオール」という打撲傷の時に湿布として用いる薬を製造・販売する星製薬を設立。大胆な広告宣伝、一村に一軒ずつの特約販売店制(いまでいうボランタリー・チェーン・システム)などまったく新しい商法で、星製薬を急成長させていった。さらに、大正に入ってからは、日本の製薬会社として初めて麻酔剤、モルヒネの精製に成功。日本国内でのモルヒネ精製を一手にひきうけ、会社は、活況を呈していた。
市郎の入社後大正8年には、モルヒネからさらにコカイン、キニーネなどのアルカロイドをも手がけ、星製薬は、まさに製薬会社のトップランナーであった。
星製薬の大崎工場に入社した市郎にとってクスリ作りはまったく初めての体験だった。市郎は大崎工場の錠剤製造課に配属され、星製薬の主力製品であったモルヒネ、コカインなどのアルカロイドや、胃腸薬、風邪薬などの製造にたずさわった。市郎は、工場内にあった独身寮で同じ世代の同僚たちと寄宿生活を送った。日給は40銭、月に直すとせいぜい11円ぐらい。そのうち寮に払う食費が7円40銭だったので市郎の生活は苦しかった。秋山家はあいかわらず経済状態が悪かったので仕送りもしてもらえなかった。
「あの頃はつらかった。私はふとんも満足に持っていなくて、冬など寒くてしかたなかったので、しかたなく木の机をふとんのかわりに足もとにかぶせて暖をとったりしました」(市郎・談)