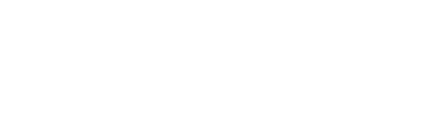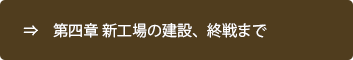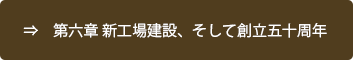秋山錠剤物語第四章 新工場の建設、終戦まで
第四章 新工場の建設、終戦までSTORY
篤志家・小島直二氏との出会い
昭和15年の秋には「皇紀2600年祝典」があったが、その頃には「秋山研究所」の工場設備は充実し、錠剤機は単式が11台、星製薬製のロータリー式が2台、それに糖衣機が2台とふえていた。
仕事は順調の一途で、やがて工場は手狭になってきた。市郎は、なんとかして工場を大きくしようと考えていたが、その資金のメドがなかなか立たなかった。そんな時、市郎は偶然の機会で篤志家・小島直二氏に出会うのである。
「私の生涯をふりかってみると、私を助けてくださった方々との出会いがいかに大切であったかを身に泌みて感じます。転機にぶつかるたびに、誰かが私を引きあげてくださった。その点、私は本当に幸運だったといえます。はじめに独立した時の吉田浩一氏との出会い、『秋山』がいちばん苦境に陥った時の原沢福康氏との出会い。そして、新しい工場を建てようとしていた時には、小島直二氏に出会うことが出来ました」(市郎・談)
昭和16年の3月だった。秋山家の親類に不幸があり、市郎は通夜に出席した。その席で偶然、小島直二氏の隣になり、聞かれるままに、「幸い仕事はたくさんあるのですが、工場が狭くて困ります」と、「秋山」の現状を語った。小島氏は、「秋山研究所」の仕事に興味を持ったようで「よかったら明日、事務所に相談しに来てくれ」といってくれた。
小島氏は、当時・東京・州崎に料亭を二軒持っていた事業家だった。早稲田大学を出てほかに鉄道弘済会の前身などにも資金援助をしていた。
「通夜の翌日、小島さんの事務所に行くとすぐに『いくら要るのか?』と話が始まりました。私は率直に『1万円あったら百坪ぐらいの工場ができる』と答えました所、『それでは貸してあげよう』とその場で、女の事務員に銀行に1万円を取りに行かせたのです。そして女の子から百円紙幣の束を受取ると、借用証書を書くこともなく利息を付けることもなく、1万円を私に貸してくれた。これにはすっかり感激してしまいました。(市郎・談)
こうして思いがけない援助者を得た市郎は、一日も早くこの資金を生かすために工場の建設にとりかかった。
新工場建設へ
土地は、現在の秋山錠剤本社の1号棟のある所に百坪を得た。
当時はまったくの原っぱで東急の分譲地として売りに出されていた。実はその土地はすでに高林勝太郎氏(後に戦後、都会議員になった)が買われていたが、市郎は、他に適当な土地がなかったので高林氏に再三、再四、依頼し、土地を借りることができた。(土地はのち昭和23年に買取る)。高林氏はこの土地にアパートを建てる計画で、設計図まで出来ていたにもかかわらず市郎の熱意にうたれ、土地を市郎に譲ってくれたのである。
こうして昭和16年の8月に、新工場は完成した。土地は百坪、権利金2千円、地代月に35円。工場建物は32坪(一階建て)住宅は二階建27坪であった。
小島直二氏は市郎の人柄を見込んで、さらに、設備資金として3万4千円を貸してくれた。市郎はそのおかげで、当時、打錠機としてもっとも性能のよかった星製薬製のロータリー式打錠機(米アーサー・コルトン社のものを改良したもの)4台を設置することができた。当時、単式打錠機は、1分間に60個ぐらいしか打錠できなかったが、ロータリー式だと、1分間に320錠、実に単式5台分の能力を持っていた。そのロータリー式打錠機を4台もそろえたのだから「秋山」の月産能力は飛躍的に向上した。(費用は4台で1万円であった)
さらに乾燥機も新しくした。ひのき造りの大型(二階式)乾燥機で、従来のものは煉炭で火を起こしていたが新しいものは、ガス・ボイラーによるもので性能は大きくアップした。
社員は約20人にふえた。そして新工場建設にともない名称も「秋山研究所」から「秋山錠剤研究所」へと改称した。
大東亜戦争始まる
「秋山」の新工場が完成した昭和16年、その年の12月8日には、日本は真珠湾攻撃を敢行し、いよいよ大東亜戦争(太平洋戦争)に突入する。
この時期はまた、日本の医薬品の生産高がふえ続けた時期である。昭和に入ってから年間生産高は1億円を超え、太平洋戦争の始まる前年、昭和17年にはついに3億円を突破し、戦前のピークを達成するのである。
そうした医薬品界の発展を背景に「秋山」も活況を続けた。受注はひきも切らず、ロータリー式打錠機は4台から11台にふえた。
この頃の製品としては太陽製薬の「ビタレイ」、三宝製薬の「ジアトミン」、鐘ヶ淵化学の「ますらお」などがある。
また、軍需用錠剤として、陸軍の健胃錠「スルファミン錠」の納入も増え続けた。工場は活況が続いた。製薬会社の間では、“技術の秋山"“納期を守る秋山“ と信用が増した。すぐ近くにあった星薬学専門学校の学生たちが初めて工場見学に来たりしたのもこの頃である。
新工場だけでは注文を捌き切れず、深川木場三丁目には分工場を2ヶ所設け、ここでは酵母基剤の整腸錠剤などを主に作った。
戦局の悪化
しかし好況は長く続かなかった。昭和18年に入ってから太平洋戦争の戦局は日本にとって悪化の一途をたどり始めるのである。
ガダルカナル撤退、連合艦隊司令長官・山本五十六元帥の戦死、アッツ玉砕、学徒兵出陣(昭和18年)。そして、昭和19年に入るとついにB29による東京空襲が始まり、「秋山」の周囲にも被害が出るようになった。
「秋山」の社員にも、会社から出征していく者がいた。
また当時、明治薬学専門学校の生徒であった秋山義郎二代目社長は、その頃のことを次のように語っている。
「親父は会社の仕事に一生懸命でしたが、僕は仕事のことなんか考えられなかった。何故って、学徒兵の動員が始まっていましたから、いつ死ぬかわからない毎日だったのです。幸い戦地には行かずにすみましたが、あの時はどうせ長くない命だとあきらめて日本中を見ておこうとあちこち見て歩きました。これがこの世の最後だと思って…青春の思い出をつづって残しておこうと思ったのもこの頃です」
戦局の悪化に伴い、産業界では企業整備が行われた。製薬会社にも整備令が発令され、錠剤界も製薬部門と見なす、ということになった。当時、東京錠剤組合(市郎もその理事の一人として活躍していた)には約45の錠剤会社が加入していたが、企業整備令の発令の結果「秋山」社が残存され、他は全部整備されてしまったのである。
だが戦争も末期になると、次第に材料にもこと欠くようになり、満足に薬を作れる状態ではなくなっていた。すでに昭和16年には砂糖が手に入らなくなり、糖衣錠を作ることは出来なくなっていたし、19年も末の頃には、電力制限も厳しくなって錠剤作りどころではなくなっていた。さらに悪いことに、昭和20年には、社員の不始末によって工場の一部を焼失、生産能力は大きく低下してしまった。
空襲、そして終戦
昭和20年に入ると、B29による東京空襲は激しさを増した。2月の大空襲に続く、5月の東京大空襲はついに「秋山」も襲い、市郎は、焼夷弾のために右足を骨折してしまうのである。
5月23日、夜、その夜のことを市郎は次のように語っている。
「その夜、私は町内会の世話役(郡長)をしていましたので任務として町内を見まわっていました。
空襲はいつもよりすごく、空は真赤になっていました。私は家族のことが心配で、家に戻ってきたのですが、門に入るや、焼夷弾が家に落ちてきた。幸い、それは不発弾だったのですが、破壊された木材がものすごい勢いで右足にぶつかり、私はそのまま倒れてしまったのです。(市郎・談)
防空壕に避難していた家族は、市郎を助け、当時、池上にいた妻・ケイの父親を頼っていった。工場も、住宅もこの時類焼してしまったのである。
市郎の傷は重く、始め昭和医大に運ばれたが負傷者でいっぱいで見てもらえず、3日後、本郷の東大病院・整形外科に入院した。診断は右足複雑骨折だった。
「入院したといっても当時の病院はひどいものでした。ベッドは汚なく、シラミもノミも南京虫もいました。薬も満足になく、治療は思うようにいきませんでした。でも、あの大空襲で、足が悪くなっただけというのは考えてみれば幸運だったかもしれません」(市郎・談)
市郎は、東大病院のベッドで8月15日を迎えた。工場は、全焼していたし、市郎自身も十月末には退院したものの歩行は困難で、前途は、まったくわからない状態だった。